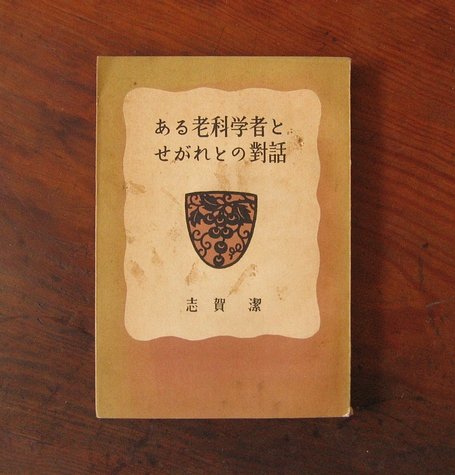|
《志賀博士は、丸顔の小さなお爺さんだった。村夫子然たるもんぺいをはいていられたので、余計小さく見えた。自分で修繕した眼鏡をかけて、ポール・ド・クライフの『細菌の猟人』を読んでいられた。僕たちの突然の来訪を非常に喜ばれて、とっときの煙草などの封を切って、すすめられるのだった。病身の息子さんと、その奥さんと、三人のお孫さんが一緒に暮らしていられた。随分貧しい暮らしのように見受けられた。障子一面に新聞紙が貼ってあった。つまり、障子紙の代りに新聞紙を使ってあるのだった。だから部屋が重苦しく暗かった。僕は撮影の旅で、方々の農村も歩いたが、こんなひどい障子は初めてだった。志賀博士が明治三十年に赤痢菌を発見して以来、今日までに人類が受けた恩恵は、決して少なくない筈である。しかもここに、その発見者は、赤貧洗うが如き生活に、余生を細らせているのである。僕たちはひどく矛盾を感じないわけには行かなかった。博士は僕たちが所望したので、文化勲章を見せて下すったが、勲章というものは凡そ貧乏臭さのないものだけに、ボロボロの畳の上で見ると、その金銀のあでやかさも、何かそらぞらしいものに思えた。「自分の選んだ学問を通じて人類の福祉に貢献する事。それだけである。而して自分の五十年の仕事は貧しいながらその為の捨石にはなり得たであろう。これが私の自らひそかに慰めとする所である」と博士は「私の信条」に書いていられるが、博士のような人に対して、僕たちとして、それで済むわけのものでない。その日の夕暮れ、僕たちは博士一家の人々と、丘の上と下で、手を振りながら別れを告げた。お孫さんたちが、いつまでも小さな手を振っているのが、何か切なかった。やがて、それも松林の陰に見えなくなった。僕たちは、砂地の道をポクポク歩きながら、思い思いの考えに沈んでいた。》 (土門拳『風貌』より) |