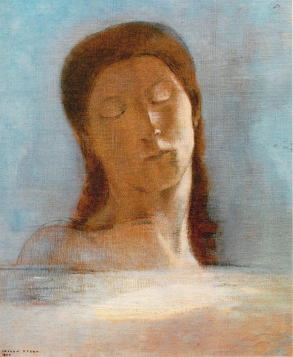 |
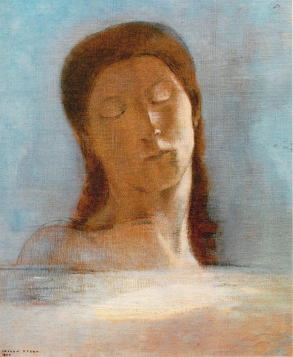 |
|
アルバート・アインシュタイン |

|
「親しい者の死、これに耐える道はない。苦しみぬいた末、ようやく私は次のように考えるようになった。ある人間が生きている、というのは私にとってどういうことか。私にとっては、その人間の顔が見え、声がきこえる、ということにほかならない。とすれば、たとい死んだ人間であっても、その顔が見え、その声がきこえている以上、私にとってはその人間は生きているのと少しも変わらない。そう考えて、かろうじで私は自分をなだめることができた。」 アルベルト・ジャコメッティ |

|
「でも何といっても、私の好きなのは、この平衡台を渡ってゆくことだったの。そのころ、すでに、それは、平衡感覚を矯正してゆく快感の追求から、高いところを渡ってゆく緊張感とそれが生みだす快感の追求に変っていたのね。ある恐怖にさらされている感じ、それは、まるで、嵐の風に顔を吹かれている感じみたいだと思ったわ。緊張して、何もかも忘れて、じっと油汗をにじませて渡ってゆくこと・・・これほど私に生きているという実感を与えてくれるものはなかったの。このいい知れない抵抗体に向って、自分が、それを身体で突っきってゆくという実感・・・それはたしかに快感にちがいなかったのだけれど、いったい、この抵抗するものは、何かと考えると、その実体は、どうしても、つかめなかったのよ。恐怖でもないし、義務でもないし……。で、最後に、私は、それは、ひょっとしたら、死という厳然とした存在に感じる抵抗感ではないか、と思うようになったの」 辻邦生『廻廊にて』より |

|
「未知生、焉知死」 『論語』(先進第十一より) |